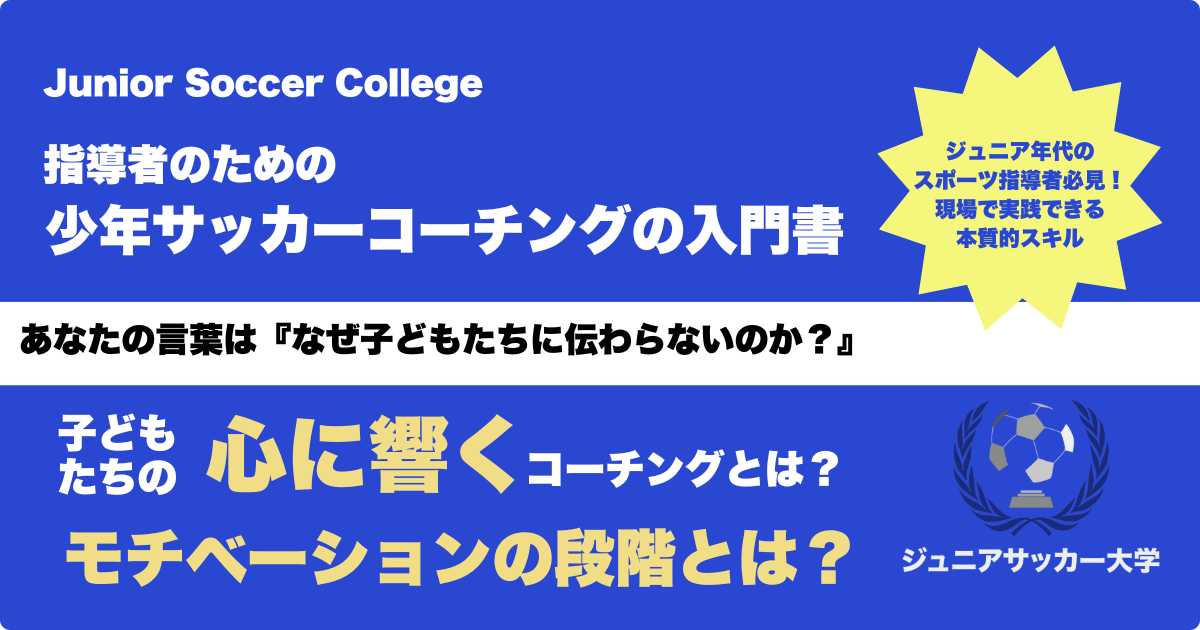こんにちは、講師のカズです。
サッカーの指導現場では、コーチングの質が選手の成長に大きく左右します。
・子どもたちに色々指導するけど、なかなか伝わらない
・言うことを聞かない子どもたちに、どう対処したらいいかわからない
・子どもたちが自分の話を聞いてくれに
このような悩みや問題は、指導者として誰しも通る道だと思います。
ただ、これはテクニカルな問題ではなく、コーチングの本質的な考えを理解していないことが原因になっていることが多いです。
本質さえ理解できれば、あなたのコーチングは劇的に変わるはずです!
※この記事は、過去に僕が電子書籍としてまとめたもののブログ版です。
また、この書籍の後半部分に出てくる「コーチングとブランディング」の関係。
ブランディングに関しては坪井健太郎氏との対談本で詳しく解説しています。
では、ここからが本題です。
指導現場において、コーチングで悩む方は、ぜひ読んでみてください!
※第1章は無料で読めます!
書籍の概要を知りたい方!(無料)
では、ここからが書籍の内容です。
指導者のための
【少年サッカー・コーチングの入門書】
はじめに

最初に皆さんに質問です。
『あなたが指導している子どもたちは、あなたが望むような行動や振る舞いを行ってくれていますか?』
『あなたのコーチング(声かけ)は子どもたちに響いていますか?』
『あなたのクラブは人気があり多くの子どもたちが通っていますか?』
もし「あまり自信がない…」という方はこの本を読むことで悩みや問題が解消されると思いますし、読み進める価値はあると思います。
反対に「とても自信がある」という方は、今回は縁がなかったということで残念ですがここで本を閉じましょう。
この本は教科書的なコーチングの考え方やテクニックについてのハウツーではなく、実際の指導現場で活かすための本質的なものを書いています。
また僕の専門はサッカーですが、その他のスポーツに共通している部分が多くあります。
「子どもたちにいろいろ指導するのだけど、なかなか伝わらない」
「言うことを聞かない子どもたちにどう対処していいか分からない」
「子どもたちが自分の話を聞いてくれない」
このような悩みや問題を抱える方は、本質的な部分を理解することでコーチングが改善されると思いますので、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
きっと子どもたちに対するコーチングの理解が深まるだけでなく、様々な指導現場で起きている問題を解決する手助けになることと思います。
また、この本では僕独自の切り口で解説している箇所が多々あります。
これらはきっと皆さんが現場で感じているけど言語化できていない部分や、改善の方法がわからない部分のヒントになることと思います。
他にも指導者のコーチングがクラブの会員数増減と関係するなどといった、クラブ運営も含めて今まであまり意識してこなかった面の理解も深まると思います。
この本を読み終えたら、あなたなりにアレンジをして指導現場で試してみてください。
そして試行錯誤をしながら、あなた自身のコーチングスキルを獲得してほしいと思います。
申し遅れました。
僕は「ジュニアサッカー大学」という名前で育成年代のサッカーにおける様々な情報を発信しているKazuと申します。
現在僕はサッカーのクラブチームを経営・運営し、そして日々指導現場に立っています。
小学生から中学生まで幅広い年代の子どもたちに指導しており、指導歴はもうすぐ30年になろうとしています。
現在はサッカーコーチを職業にしていますが、最初は少年団でのボランティア指導者からスタートし、その後クラブチームを立ち上げ、多い時でクラブ会員数は350名ほどになりました。
30代でスペイン・バルセロナにサッカーコーチ留学し、スペイン指導者ライセンスを取得し現在に至ります。
自分の様々な経験をもとに、多くの指導者の方々に何か伝えられないかという思いから、YouTubeやブログで情報発信を始めました。
嬉しい事に現在ではYouTubeの登録者数が2万人を超え、Twitterやポッドキャストなど各ソーシャルメディア累計で3万人ほどの方々にフォローして頂いています。
海外で学んだ経験や難しい理論、様々な知識を『実体験を通じて現場で活かせるように言語化・体系化』して皆様と共有させて頂いています。
この本もリアルな指導現場で悩む方々へ向けて、僕が経験して実際に上手く行ったものだけを凝縮して皆様にお伝えできたらと思います。
一つ注意点です。
サッカー界では「コーチング」には3種類の方法があると言われています。
シンクロ、フリーズ、ミーティング。
この本ではこれらの細かなテクニックの部分ではなく「コーチング=声かけ」や「普段のコミュニケーション」「マネジメント」といった幅広い意味でコーチングと表現しています。
ですので、3種類のコーチング方法のテクニカルな面に関しては解説しないのでご了承ください。
どうしても知りたい方はお手数ですが、僕のブログに書いているのでそちらを参照してください。
第1章『コーチングは文脈が一番重要』
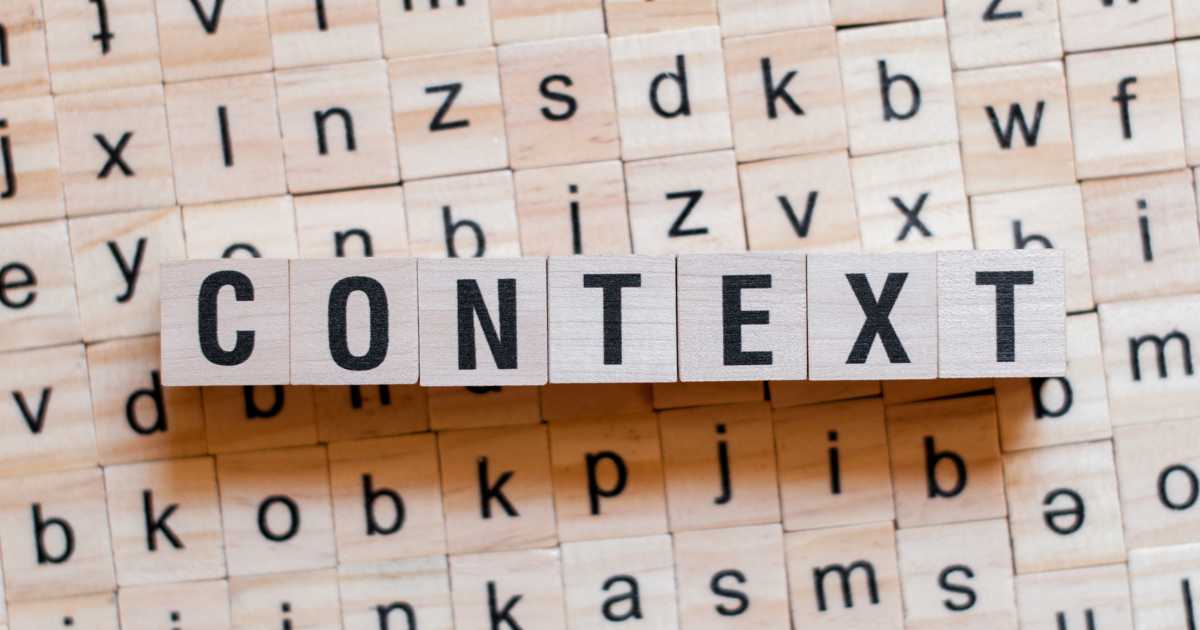
最初にいきなり結論ですが、本書で伝えたい内容を一言で表現すると
『適切なコーチングを行うためには、子どもが置かれている文脈を理解することが一番重要』
ということです。
これ以上言うことはありません。
適切なタイミングで適切な言葉を投げかける。
これが全てです。
なるほど!と思われた方はここで読み終えても大丈夫です。
ご愛読ありがとうございました!
というのは冗談です。
反対に「どういうこと?」と思われる方は読み進めてください!
①子どもが置かれている文脈を読み取る
文脈とは何かというと、子どもたちが現在どのレベルや段階にいて、どんな性格で、どのようなものを欲しているのか。
子どもたちが次のステップを踏むにはどのようなアプローチが効果的なのか。
このように子どもが置かれている状態です。
一口に子どもたちと言ってもサッカーを始めたばかりの子どももいれば、サッカー選手になりといと日々努力している子どももいます。
サッカーに興味を持っている段階なのか、夢中になっている段階なのか。
挫折している状態か天狗になっている状態か。
その子に欠けているものは何か、その子の長所は何か。
このように一人一人置かれている状態は違います。
この文脈を抜きにして効果的なコーチングを行うことはできません。
考えてみれば当然のことですが、僕ら指導者はここを見落とすことも多々あります。
『適切なタイミングで適切な言葉を投げかける。』
これこそがコーチングの本質の一つであると僕は考えています。
僕がYouTubeやメールで質問を受けた時にはいつも「実際の現場を見ていないので分からないのですが」と前置きをして話すのはそのためです。
コーチングでも戦術指導でも全て子どもたちの文脈を観察し、理解した上でないと何とも言えないからです。
②画一的な方法はない
文脈が重要である、ということは画一的な方法がないということ。
よくある質問で「子どもは褒めて伸ばした方が良いのか、それとも厳しく育てた方が良いのか」。
このような二元論的な考えは実際の指導現場では上手くいきません。
褒めることは大切だし、認めることも大切。
時には叱ることも必要だし、ユーモアを交えて楽しませる必要もあります。
僕ら指導者はどうしても「唯一の正解があるのではないか」と考えがちですが、そんなものはありません。
常に子どもたちを注意深く観察し、どんなタイミングでどんな言葉を投げかければポジティブな変化が起きるのかを考えなくてはなりません。
③何にでもメリットとデメリットがある
叱るにしても褒めるにしても、それぞれにメリットとデメリットが必ず存在します。
練習前に良い雰囲気を作ろうとしてユーモアを交えて話すと、子どもたちとの良い関係が生まれますが、話しすぎると練習の最初が締まらないという現象も起きます。
自信を失った子どもに対して褒めたり励ましたりすることは大切ですが、それもやり過ぎると天狗になったり。
コーチングに関わらずどんなものにも必ずメリットとデメリットがある。
そのため、どのような方法を用いるのかは、文脈を考慮した上で考えなくてはなりません。では、そのような文脈をどのように読み取っていくのか。
そして子どもたちに影響を与えるコーチングとは何かを解説していきます。