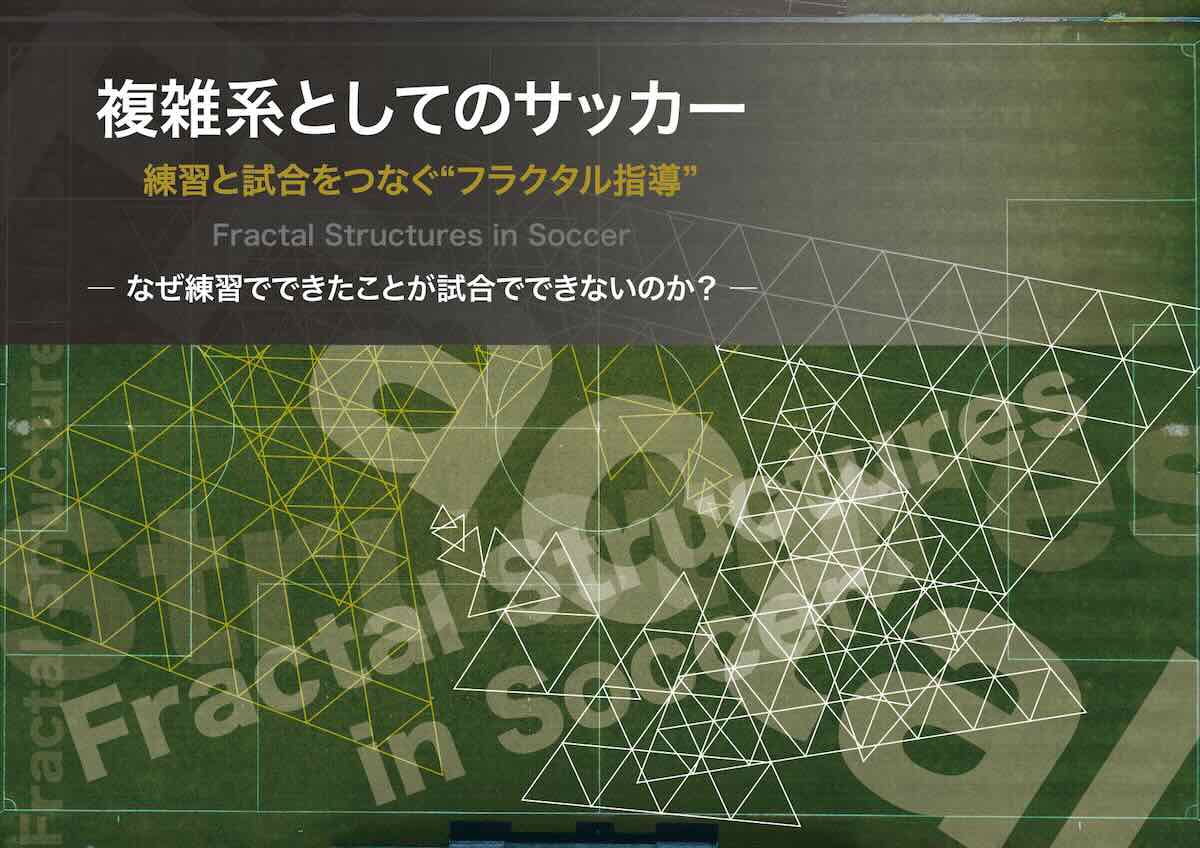こんにちは、講師のカズです。
サッカーの指導をしていて、こんな疑問を感じたことはありませんか?
・「練習ではできていたのに、なぜ試合ではできないのか?」
・「試合から逆算して練習メニューを作るのが難しい」
・「試合で戦術的な指示を伝えるのが難しい」
僕自身、長年指導現場で試行錯誤してきた中で、この問いと何度も向き合ってきました。
そして辿り着いたのが、**“サッカーは複雑系のスポーツである”**という考え方。そしてその複雑性を読み解くキーワードの一つが「フラクタル」という言葉でした。
ただし一言に「複雑系」と言っても、その概要と指導への活かし方を解説するのは膨大な量になるので、『複雑系としてのサッカーシリーズ』として、様々なキーワード毎に解説します。
その第一弾が「フラクタル」。
このまとめ記事では、僕が電子書籍として執筆している『複雑系としてのサッカー:フラクタル指導』の全体像を紹介します。
各章はプレミアム会員限定記事として公開中ですが、このページでは全体の要約と読みどころを無料でご覧いただけます**。
このシリーズで伝えたいこと
①なぜトレーニングでできたことが試合で再現されないのか?
②なぜ原則を教えても、選手の判断がバラバラになるのか?
③サッカーにおける“本質”や“再現性”とは何か?
これらの問いに、フラクタルという視点から一貫性を持って答えることが、この書籍のテーマです。
電子書籍版
概要を聞きたい方
では、解説します。
第1章:複雑系とフラクタル
サッカーが「複雑系のスポーツ」であるとはどういうことか?
その核心を「フラクタル(相似構造)」という概念から解説します。
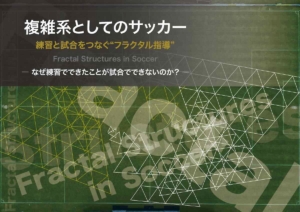
第2章:サッカーの本質としてのフラクタル性(本質の相似性)
サッカーの“本質”とは何か?
『サッカーはサッカーをすることで上手くなる』には“本質”を理解しなければいけません。
人数が変わっても本質が変わらない構造に「フラクタル性」が潜んでいます。
1対1ではサッカーは成立しない?
サッカーの最小構造とは?
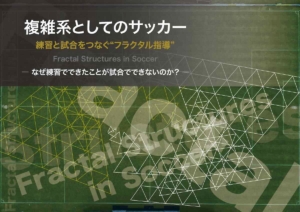
第3章:構造としてのフラクタル性(形や動きの相似性と階層性)
三角形のサポート構造や、守備ラインのスライド── 局所でも全体でも同じような“形と動き”が繰り返されている。
この「構造のフラクタル性」が、選手の迷いを減らし判断を速くする理由とは?
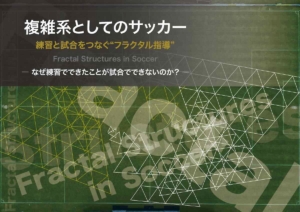
第4章:原則としてのフラクタル性(概念的な相似性)
パスコースがなない時はどうする?
その判断は、個人でもチームでも“共通する原則”です。
プレイモデルや原理原則も、普遍的な部分が“フラクタル”に機能します。
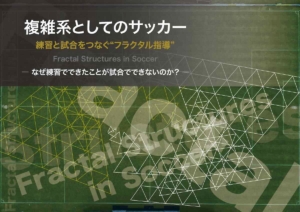
第5章:フラクタルな指導の実践-1:トレーニング編
ロンドやポゼッション練習、あなたは「何を伝えるためにやってますか?」
人数が増えても“同じ原則”を持ち込めているか?
練習が試合につながらない指導の落とし穴と、フラクタルな再構成法。
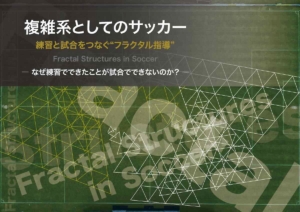
第6章:フラクタルな指導の実践② 〜ゲーム(試合)編〜
試合中にトレーニングの原則をどう再現させるか。
自己組織化を引き出す“コーチングのフラクタル性”とは?
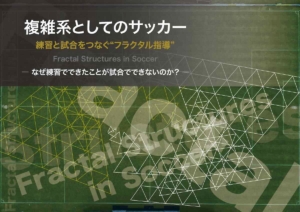
最後に
このシリーズは『複雑系としてのサッカー』における、その概念や指導方法を理解するためのキーワードの一つである「フラクタル」という概念を通じて、サッカー指導の再現性・本質・原則を一貫して理解するためのヒントを解説しています。
次回作では、**「自己組織化」や「創発現象」**といった、さらに深い“複雑系としてのサッカー”を取り上げる予定です。
続きを読みたい方は、ぜひプレミアム会員へご登録ください!
※プレミアム会員はすべての有料記事が読み放題です。