こんにちは、講師のカズです。
2020年代、AI時代の到来により、教育や指導のあり方が根本的に変わろうとしています。
特にサッカー指導においても、これまでの「答えを教える」指導から「問いを立てる」指導への転換が求められる時代に入っています。
しかし、以下のような悩みを持つ指導者の方も多いのではないでしょうか。
・AIが普及する中で、指導者としての価値をどう見出せばよいかわからない
・従来の指導方法が通用しなくなるのではないかという不安がある
・新しい時代に求められる指導者像がイメージできない
この記事を書いているのが2025年7月。
僕自身、昨年10月からAIを本格的に活用し始め、現在は5つの有料AIツールを使いながら、この変化の中で指導者としてどうあるべきかを考え続けています。
この記事では、AI時代における学びの本質から、これからのサッカー指導者に求められる新しい役割まで詳しく解説します。
この記事を読めば、AI時代における指導者としてのポジションが明確になり、より価値ある指導ができるようになると思いますので、最後までご覧ください。
1. AI時代が変える「学び」の本質

①正解を求める時代の終焉
AI技術の発達により、答えが決まっている問題に対しては一瞬で正解が出るようになりました。
これまでの受験勉強のような「暗記型学習」は、AI時代においてその価値を失いつつあります。
例えば、問題集を解いて正答率を競うような学習方法は、AIを使えば全員が100点を取れる状況になります。
つまり、決まった答えを導き出すスキルでは、もはや差別化を図ることができなくなってしまうのです。
②学びの本質は「楽しさ」にある
僕が好きな某作家の方が言っていた「人はなぜ勉強するのか?それは楽しいからだ。」という言葉があります。
これこそが学びの本質だと思うのです。
現在の学校教育では、テクニカルな受験テクニックや「やらなければいけない勉強」が重視され、なぜ学ぶのかという本質的な部分が教育されていません。
これは現在の日本の教育システムの重要課題とも言えるでしょう。
③自発性・自由性・独創性こそが価値
AI時代における学びの本質は、遊びのような自発的で自由で独創的なものです。
決まった答えを当てるだけのゲームではなく、答えのない問題に対してどうアプローチするかが重要になります。
これまでのように「みんなと同じ答えを導き出すスキル」ではなく、「常識を疑い、自分なりの問いを立てること」が最高の価値を持つ時代になってきています。
ケビン・ケリーが説く「常に問い続ける練習・習慣」
ケビン・ケリーという方の『5000日後の世界』という書籍には、非常に興味深い提言が書かれています。
ケビン・ケリーは、AI時代において人間にしかできないことは「常に常識を疑うこと」であり、「問いを立てる」自分なりの問いを立てることの習慣を持つことこそが最高の価値になってくると述べています。
つまり、みんながみんな同じ答えを求める時代において、AIを使えばわからなくても同じ答えが出る。
そうした中で、それを疑う、もしくは別の切り口で考えることができないか、という意味で常識を疑うことや自分なりの問いを立てることが価値を持つようになってくるのです。
今まではみんなと同じように答えを導き出すようなスキルに価値がありました。
それは個体差があったからです。
学校の勉強でも個体差があって、その個体差によって行ける高校や大学が変わってきました。そこで差別化が図られていたのです。
しかしAI時代になったら、そんなものもみんな同じになってくるから差別化できません。
そうした時に、答えがないものを思考する、考える、問いを立てることができるかどうか、そういうところが唯一の人間の価値になってくるのです。
2. 指導者の役割転換:ティーチャーからファシリテーターへ
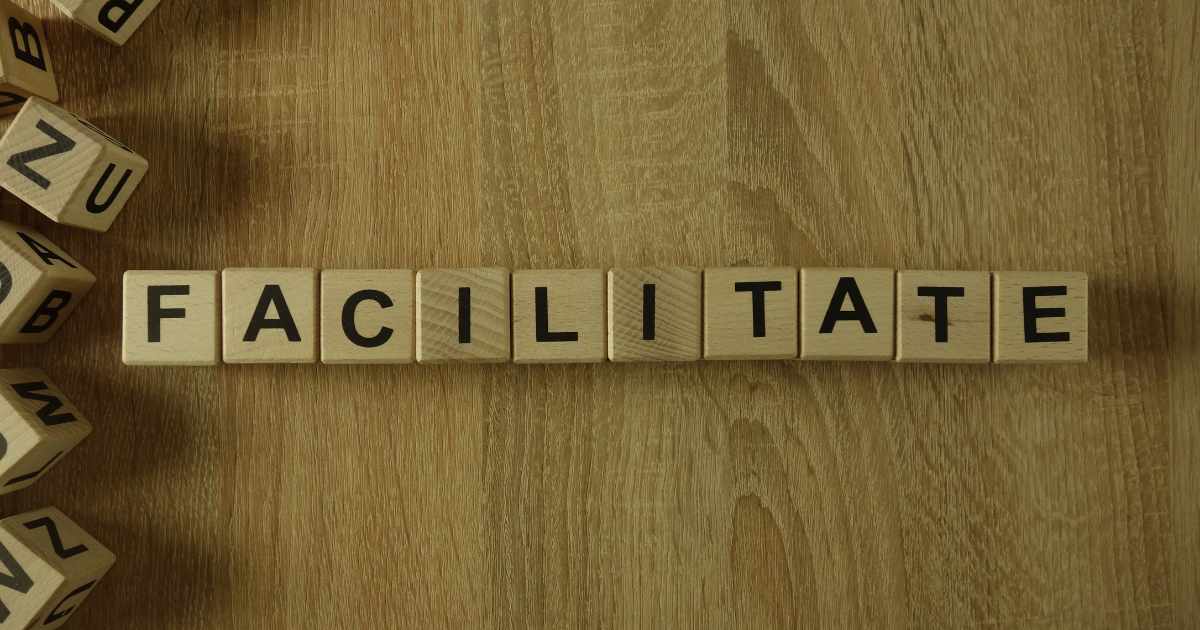
①「答えを教える人」の排除
とあるヨーロッパの教育現場では、「答えを教える人」という概念を積極的に排除する動きがあります。
なぜなら、AI時代においては生徒がAIに質問すれば瞬時に答えが得られるからです。
従来のティーチャー(教える人)としての価値は、AIによって完全に代替されてしまいます。
では、教育者や指導者はどのような役割を担うべきなのでしょうか。
②ファシリテーターとしての新たな価値
これからの時代に求められるのは、ファシリテーターとしての役割です。
AIには難しい「共感」や「一緒に問いを立てる」といった人間らしい部分は、やはり人間がやるしかありません。
30人のクラスがあれば30通りの学び方があります。
一律的な指導ではなく、一人ひとりに寄り添い、それぞれの自発的な学びを促していく。
そして自由な発想や独創的な答えを大切にしていくことが重要になります。
なぜなら「決まった答えを探す」ことでは差別化が図れず、その行為自体に価値がなくなるからです。
決まっていない答え、もしくは不確実なもの、予想しなかったようなもの、これらを発想できるスキルこそが重要になってきます。
③コンサルタント業界に見る変化の先行事例
この変化は既に様々な業界で始まっています。
例えば、コンサルタントの仕事についても「なくなる」と多くの人が言っています。
これはどういうことかというと、何らかの知識を教えるような仕事、つまり誰も知らないような知識を持っていて、それを一定の答えとして知らない人に教えるような職業は価値がなくなっていくということです。
なぜなら、そのような知識はもうAIに聞けば瞬時に答えが得られるからです。
従来のコンサルタントが提供していた「答えを与える」サービスは、AI時代においては意味を失ってしまうのです。
③僕のサッカー指導における実体験
僕自身、スペインでサッカーを学んだ経験から、当初は「教えたい」という気持ちが強かったのですが、ここ数年で「選手の自由で独創的なアイディアを引き出す」方向にシフトしてきました。
また「決まったフォーメーションがないサッカー」というものも実験的に取り組みました。
こられの取り組みの背景には、「教えるよりも、もっと独創的なアイデアを」という背景があります。








