こんにちは、講師のカズです。
※この記事では、読者さんから寄せられた質問に回答する形で、テーマについて深掘りしていきます。
ジュニア年代のサッカー指導では、「認知の向上」がとても重要です。
しかし、「どうやって認知を鍛えればいいの?」と悩む指導者の方も多いのではないでしょうか。
僕自身、過去には「子どもたちがパスを受ける前に周りを見ていない」「試合中の判断が遅い」といった問題に直面し、どう指導すべきか試行錯誤していました。
そこで、この記事では以下の3点を中心に解説します。
・認知を向上させるトレーニング方法
・戦術と技術を同時に鍛えるトレーニング
・実際の試合とリンクした効果的な練習の考え方
この記事を読めば、認知・戦術・技術を総合的に向上させるためのトレーニングの考え方がわかり、実践に活かせるようになると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください!
1. 認知を向上させるトレーニングとは?

① 認知とは何か?
「認知」とは、サッカーにおいて状況を把握し、適切な判断をする力のことです。 例えば、
・味方や相手の位置を素早く確認する
・ボールを受ける前に周りの状況を把握する
・最適なプレーを瞬時に選択する
こういった要素がすべて「認知」に関わっています。
② 認知を鍛えるためには?
僕の場合は、「認知を鍛えるトレーニング」という考え方は今の所しません。
どちらかと言うと、それに特化したトレーニングを 行うというよりも、サッカーを全体的にトレーニングする中にそういった要素があるというイメージです。
認知は常に戦術的なアクションやテクニックアクションとも関わってきますので、それだけを切り離してトレーニングを行うというよりは、全体をトレーニングする中で認知の部分も向上させるといった考えです。
2. 戦術と技術を同時に向上させるには?

戦術と技術を同時に向上させるトレーニングの解説の前に、サッカーにおけるトレーニングの方法とはどのようなものがあるかを解説します。
① トレーニングメソッドの考え方
サッカーのトレーニングには、大きく分けて3つの方法があります。
1.アナリティコ(ドリルトレーニング)
・例:コーンドリブル、リフティング、パス&コントロール
・メリット:特定の技術を繰り返し練習できる
・デメリット:試合状況と乖離しやすい
2.グローバルトレーニング
・例:4対2のロンド、5対5のポゼッション、8対8のゲーム
・メリット:戦術・技術・認知を同時に鍛えられる
・デメリット:指導者が適切なフォーカスをしないと効果が薄い
(あくまでも僕の考えです)
3.システミコ(試合に近い形でのトレーニング)
※ グローバルトレーニングにプレイモデルを足したものとイメージしてもらえれば大丈夫です
・例:試合の特定の場面を再現したトレーニング(グローバル)
・メリット:実際の試合とリンクしやすい
・デメリット: パターンになってしまう可能性がある
以上が各メソッドの特徴です。
② おすすめは「グローバルトレーニング」
戦術と技術を同時に鍛えるには、グローバルトレーニングがお勧めです。
例えば、5対5のポゼッション練習では「スペースの認知」や「 戦術的な動き」「パス やコントロールの技術」を同時に鍛えられる。
特に同数で行う場合には、必然的にプレッシャーがきつくなるため、テクニックアクションの向上にもつながります。
僕の場合は「サッカーはサッカーをすることで上手くなる」という考え方が基本です。 そのため、試合に近い形のトレーニングを多く取り入れることで、自然と認知力も鍛えられます。
3. グローバルトレーニングのポイント
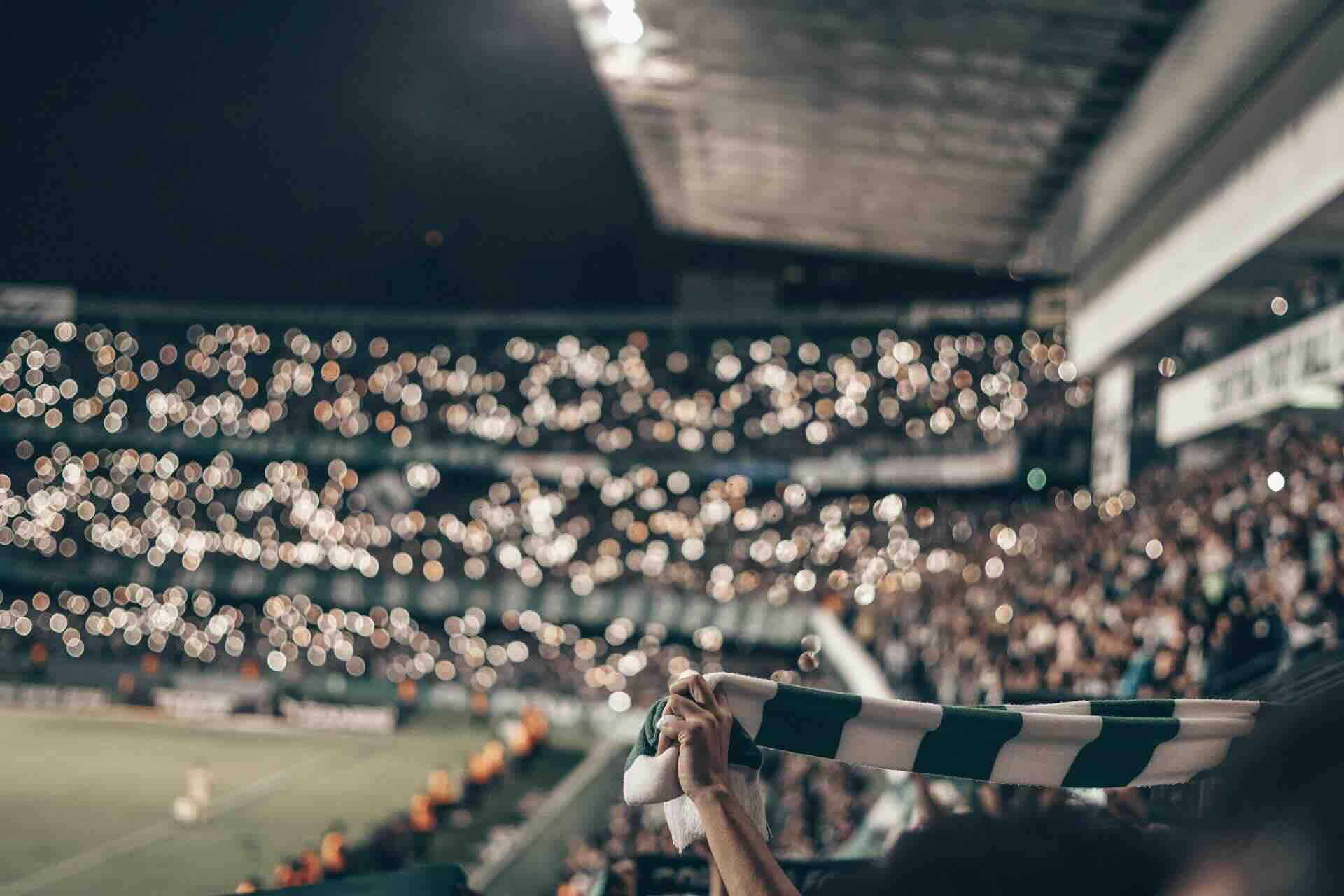
① 何にフォーカスするかを明確にする
グローバルトレーニングを行う際、指導者が**「何を伸ばしたいのか?」**を明確にすることが重要です。
例えば、5対5のポゼッションをするとき。
・「サポートのポジショニング」にフォーカスするのか
・「個人のテクニック(ファーストタッチ・パスの精度)」にフォーカスするのか
これによって、同じメニューでもトレーニングの質が大きく変わります。
② トレーニングと試合をリンクさせる
トレーニングが試合と乖離しないよう、常に「試合でのどの場面とつながっているのか?」を意識することが重要です。
例えば、
・4対2のロンド → 試合中の数的優位の状況?
・5対5のポゼッション → プレスがきつい中でのボール保持?など。
このように、トレーニングと試合の共通点を見つけ、選手にも理解させることが ポイントです。
まとめ
今回の記事では、認知を向上させる&戦術・技術を同時に伸ばすトレーニング方法について解説しました。
・認知力を鍛えるには、ゲームに近い形でトレーニングすることが重要
・戦術と技術を同時に向上させるには、グローバルトレーニングがおすすめ
・グローバルトレーニングを行う際は、「フォーカス」と「試合とのリンク」を意識することが大切
皆さんの指導現場でも、ぜひグローバルトレーニングを取り入れてみてください!








