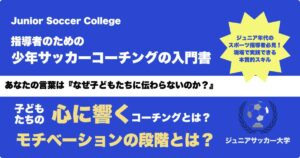こんにちは、講師のカズです。
今日は、読者の方から頂いたご質問について解説します。
以下、質問の要約です。
読者の方からのご質問
年長〜小2の子どもたちを指導していますが、意識・やる気・集中力の差が激しく、学級崩壊のような状態に…。私はサッカー未経験でどう指導してよいかも分からず、困っています。やる気のある子とそうでない子への対応、崩れた空気の立て直し方、どうすればいいでしょうか?
1. マネジメントの本質は「子どもを惹きつける力」

① 練習メニューよりも「惹きつけ力」が大事
僕の経験上、チームやグループの雰囲気があまり良くない時に、「何の練習をすればいいのか」「どんな指導テクニックが必要か」と考えてしまいがちですが、その前に重要な部分があります。
それは「指導者が選手を惹きつけているか」という本質的な部分です。
僕自身の経験からも言えるのは、指導がうまくいっている時は、子どもたちが自然と話を聞いてくれるし、練習にも前向きに取り組みます。
それはつまり「コーチの話を聞きたい」「一緒にいたい」と思わせる存在であるかどうか。
これは練習メニューや知識ではなく、信頼とキャラクターの魅力によって築かれるものです。
② 子どもを引きつける“刺激”があるか?
特に低学年では、「優しいだけ」だと子どもはなかなか惹きつけられません。
もちろん怒鳴る必要はないですが、楽しい・ちょっと面白い・でも叱る時はビシッとという、ある種の“メリハリある刺激”が必要です。
僕の場合、オフの時間でも子どもとたくさん話したり、笑わせたりして距離を縮めつつ、練習中は厳しくもある。
その両面を持つことが、結果的に子どもの心を掴む力につながっていると感じます。
この辺に関しては、僕の電子書籍「指導者のための:少年サッカー・コーチングの入門書」で詳しく書いています。
2. やる気の差にどう対応するか?

① 明確なルール設定が信頼を生む
練習中に集中できない子、ふざけてしまう子、よくあります。
ここで大事なのは「どこまでがOKで、どこからがNGか」をはっきり伝えておくこと。
例えば僕のチームでは、「ふざけて友達の邪魔をしたら即アウト」「ミスを笑ったら練習から外れる」など、人としての振る舞いに関わる部分は厳しく指導します。
逆に、気分が乗らない・疲れている子には無理をさせません。
この“叱る基準”があいまいだと、子どもたちは不安定になり、やりたい放題になる可能性が高くなります。
そのような状態が日常化していくと、何かのきっかけ次第でチームは崩壊します。
というか、いきなり崩壊するのではなく、すでに崩壊に向かって進んでいる状態です。
② やる気のある子を守る優先順位
「やる気のない子」にばかり対応していると、「やる気のある子」が冷めてしまう…というのもよくある問題です。
この場合は、やる気のある子を優先してサポートすることが大切です。
やる気のない子を無理にやらせるのではなく、周りの雰囲気や憧れから「やってみたいな」と思えるような環境づくりが効果的です。
『優先的』と書きましたが、厳密には『やる気のある子に、チーム全体の雰囲気が引っ張られる』ようなイメージです。
3. 崩壊した空気は立て直せる

① 低学年なら立て直しは十分可能
このようなチーム・グループ崩壊に直面すると「もう自分では立て直せないのでは…」と不安になってしまいますが、まだ低学年です。
立て直しは可能ですし、むしろ指導者として成長するチャンスです。
高学年や中学生くらいになってしまうと、信頼の再構築はもっと難しくなります。
今のうちに、関係性を見直してチームを立て直しましょう。
② 自分のスタンスを見直す
優しい、謙虚、でも少し自信がない…。
このようなタイプの方が、低学年指導に向いていることも多いです。
ただし、その良さが子どもに届く“強さ”に変わるためには、自己表現と判断の軸が必要です。ルール、声かけ、遊びの工夫など、自分なりにできることから始めていきましょう。
4. まとめ
・指導で大事なのは「子どもを惹きつける影響力」
・やる気の差には、明確なルールと優先順位で対応
・優しいだけではなく、メリハリのある刺激が必要
・崩壊しても、低学年なら立て直しは十分に可能
この記事では、未経験コーチの悩みをもとに、低学年指導の本質と対応策について解説しました。
ぜひ皆さんの現場でも参考にしてみてください!
※ポッドキャストでも聞けます。(むしろ細かなニュアンスが伝わるかと思います。)