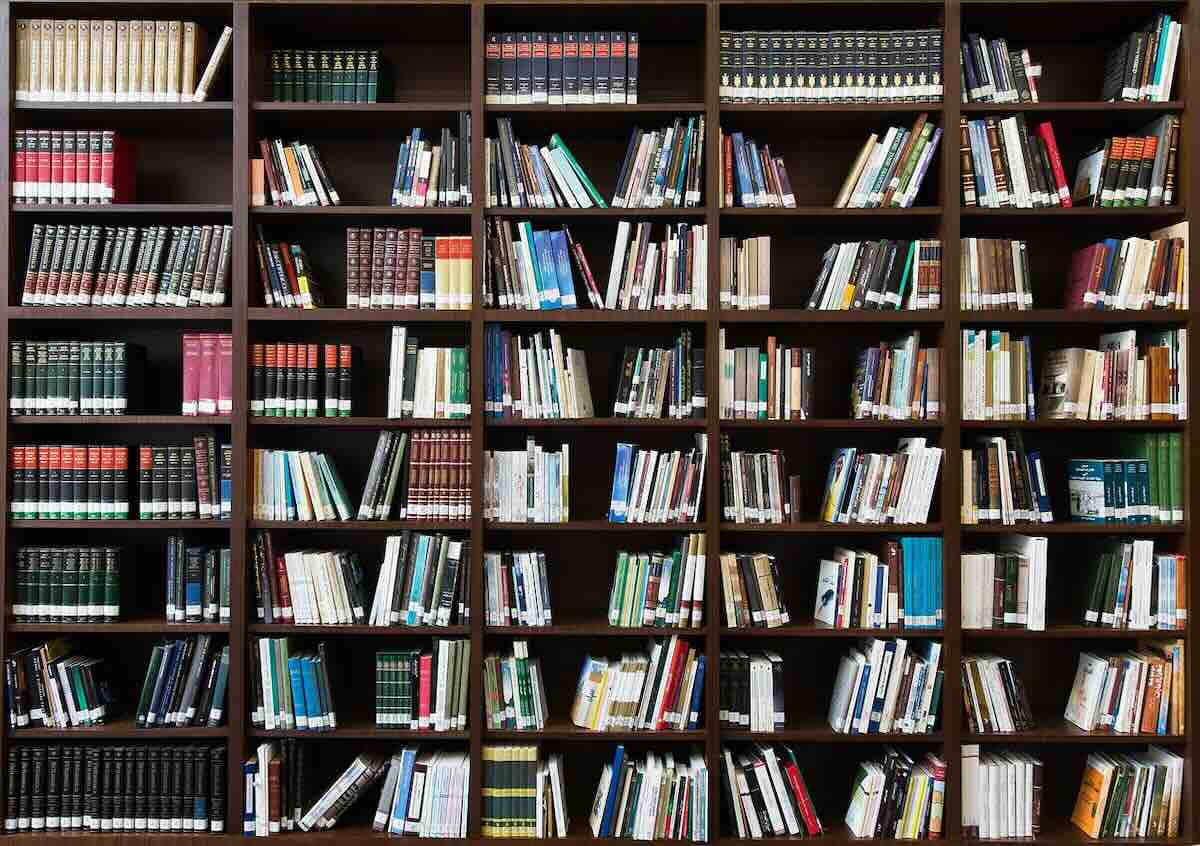こんにちは、講師のカズです。
この書籍に出会ったのは、今から約1年半前。
僕の指導経験の中で5年〜10年くらいで起こる『指導方法の転換期』。
この書籍はそれにあたるくらいインパクトが強かったです。
僕の中でとても重要な指導理論であるため、どこかで詳しく解説しますが、とりあえず概要を紹介します。
新しい運動学習・スキル取得の理論
エコロジカル・アプローチという「運動学習・スキル習得」理論は、これからのスポーツ指導のあり方を、ひいては教育のあり方すら劇的に変えていく可能性を秘めた、指導実践や学習実践の強力な手引きとなるものです。
書籍より引用
スポーツにおける運動学習・スキル習得の理論ですが、サッカーにおける人間教育の側面、チームマネジメント、組織づくりにも役立ちます。
規定的指導 vs 制約下での自己組織化
難しい表現ですが、誤解を恐れずに表現すると「規定的指導」とは従来の方法で、一定のパターンを教えたり、繰り返し同じ動作を反復することで精度を上げるイメージ。
戦術トレーニングにおけるパターン練習のようなもの、という理解で大丈夫です。
反対に「制約下での自己組織化」とは、人間もサッカーも複雑系であるという発想のもと、何らかの制約を設けることで、選手たち(個人や集団)が自ら秩序を形成し、様々なパターンを作り出すというイメージで大丈夫です。
※この辺は「複雑系」に関する知識が必要ですが、現代サッカーにおいては基本中の基本、根幹になる考えですので、これを機に調べてみましょう。
つまり書籍のサブタイトルにあるように、『指導者が教える』のではなく、『選手が自ら学ぶ』という従来の指導方法とは逆の発想です。
エキスパートほど運動がバラバラ
バスケットのフリースローなどを例に、エキスパートほど運動動作がバラバラ。
これは同じ選手が、同じ位置からのフリースローを行った際、毎回筋肉や関節の動かし方に違いがあるということ。
つまり人間は、精密機械のように寸分の狂いもなく運動動作を行うのでなく、常にノイジーで不安定なもの。
これは「同じ運動結果を出すために、異なる複数のソリューションを持つ」ことを意味しています。
これは重要なポイントで、「テクニックスキル」でも「戦術的スキル」でも、『目的を達成するためのソリューション』は選手の数だけあるということ。
むしろ様々なソリューションを選手自らが探索し発見し、スキルとして獲得していくことが求められます。
制約主導のアプローチ
では、そのような「自己組織化」をベースとしたトレーニングをどのように構築していくのか。
そこで3種類の制約と5つの指導のポイントについて書かれています。
◾️3種類の制約
1.個人制約
2.タスク制約
3.環境制約
◾️5つの指導のポイント
①代表性
②タスク単純化
③機能的バリアビリティ
④制約操作
⑤注意のフォーカス
詳細は長くなるので割愛しますが、日々のトレーニングメニューを考える際には、この辺が重要なポイントになります。
僕の中では画期的な理論
現代サッカーの様々な理論は『サッカーは複雑系である』という前提に沿って展開されているので、この書籍の内容が難しく感じるかもしれません。
ただ、これからの数年、エコロジカル・アプローチは指導の中心をなす理論の一つであることは間違いないです。
詳細やエコロジカル・アプローチに基づいた練習メニューは、今後ブログでも書いていきたいと思います。