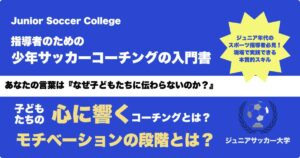こんにちは、講師のカズです。
ジュニア年代のサッカー指導では、「いつ叱るべきか」「どう褒めればいいか」という悩みを抱える指導者の方もいると思います。
特に最近は「褒めて伸ばす」という考え方が主流になっていますが、実際の現場では叱ることも必要な場面があります。
僕自身も過去には、何を基準に叱り、何を基準に褒めるべきかがわからず、一貫性のない指導をしていた時期がありました。
・結果が悪い時に叱るべきかどうか迷う
・褒めているのに子どもに響いていない気がする
・叱る基準と褒める基準が曖昧になっている
この記事では、僕が現場で実践している叱り方と褒め方の基準について、具体例を交えながら詳しく解説します。
また「褒めるではなく認めることが大切」という考えもありますが、この記事では割愛します。
この記事を読めば、一貫性のある指導ができるようになり、子どもたちの心に響く伝え方ができるようになると思いますので、最後までご覧ください。
1. 叱る・褒めるの大前提:影響力がなければ意味がない

①信頼関係と影響力の重要性
どんなに正しい叱り方や褒め方を知っていても、指導者が子どもたちに対して影響力を持っていなければ、その言葉は心に響きません。
僕が現場で最も重視しているのは、子どもたちとの信頼関係と、指導者としての存在感です。
「可もなく不可もなく」という指導者では、子どもたちにとって刺激が少なく、結果として影響力を持てません。
②影響力を持つための条件
指導者が影響力を持つためには、以下の要素が必要だと考えています:
・子どもたちを惹きつける魅力があること
・一貫した価値観を持っていること
・子どもたちの成長を本気で願っていること
・普段から子どもたちをよく観察していること
これらの土台があって初めて、叱る言葉も褒める言葉も子どもたちの心に届きます。
③「物足りない」指導者の問題
中途半端な感じでは、子どもたちにとって「物足りない」存在になってしまいます。
刺激が少なく、印象に残らない。
そのような場合、影響力を持つことができず、発した言葉は、右から左に流れてしまいます。
むしろ、時には厳しく、時には優しく、メリハリのある指導者の方が、子どもたちの記憶に残り、成長のきっかけを与えることができると思います。
2. 僕の叱る基準:結果ではなくプロセスとルール

①勝敗や結果で叱ることはない
僕の指導で最も大切にしている原則は、「コントロールできないことで叱らない」ということです。
試合の勝敗、シュートが入るかどうか、パスが通るかどうか。
これらの結果は、子どもたちが100%コントロールできるものではありません。
だからこそ、結果が悪くても叱ることはありません。
②プロセスを重視した叱り方
一方で、プロセスについては厳しく指導します。
具体的には以下の通り。
・一生懸命にプレーしているか
・チームメイトと協力しているか
・諦めずに最後まで頑張っているか
・練習で学んだことを実践しようとしているか
これらは子どもたちがコントロールできる部分なので、ここが不足している時はしっかりと叱ります。
③人間性・規律面での叱り方
技術面やプレー面以上に重要視しているのが、人間性や規律の面です。
叱る場面の例:
・時間を守らない
・挨拶ができない
・仲間をバカにする発言をする
・用具を大切に扱わない
・嘘をつく
これらについては、妥協せずにしっかりと叱ります。
なぜなら、これらは将来にわたって重要な人間力の基礎だからです。
④叱る時の具体的な方法
叱る時は、以下のポイントを意識しています。
・なぜ叱られているのか理由を明確にする
・感情的にならず、冷静に伝える
・その子の将来を考えて叱っていることを伝える
・叱った後は必ずフォローする
叱る時も、どういう伝え方が効果的かは選手のキャラクターやそれまでの文脈によっても異なります。
当然、叱るも褒めるも、画一的な方法はなく、常に文脈との関係性で決まります。
3. 僕の褒める基準:プロセスと成長を評価

①結果よりもプロセスを褒める
褒める時も、結果ではなくプロセスを重視します。
ゴールが決まったから褒めるのではなく、そのゴールに至るまでの努力や工夫、チャレンジする姿勢を褒めます。
逆に、結果が出なくても、良いプロセスがあれば積極的に褒めます。
②成長を褒める
僕が最も重視しているのは、「その子なりの成長」です。
他の子と比較するのではなく、その子の昨日と今日を比較して、少しでも成長が見られたら褒めます。
これが、子どもたちの自信につながると考えています。
相対的に評価するのではなく、その子自身なりの成長が見られるかどうかが重要です。
③具体的な褒めるポイント
褒めるケースの例を挙げておきます。
プレー面で褒める例:
・諦めずに最後まで走った
・新しいことにチャレンジした
・相手をリスペクトしたプレーをした
人間性面で褒める例
・仲間を励ました
・チームのことを率先的に行なっている
・前向きに努力している
もちろん、試合に勝った、ゴールが決まった、という結果に対してもフィードバックをしますが、それはあくまでも本質的なものではありません。
「ナイス、シュート!よく決めたね。」
と結果を誉めつつも、その後にプロセスの重要性を伝えるようにしています。
④効果的な褒め方
褒める時は、以下のことを意識しています。
・具体的な行動を褒める
・その子だけに向けた言葉で褒める
・その子の良いところを見つけて褒める
例えば、チームの中でおとなしい選手、少し自信がない選手などは、全員の前で褒めたりもします。
そうすることで、チームの中での立場、存在感が変わったりします。
今までは、自信がなくプレーしていた選手が、それをきっかけに変化していくことは、これまでも多く経験してきました。
褒めるも叱るも、個人、チームのマネジメントと密接に繋がっています。

4. 年代別のアプローチ

①低学年(1〜3年生)への伝え方
低学年では、シンプルで分かりやすい伝え方を心がけています。
叱る時:
・短い言葉で端的に
・なぜダメなのかを簡単に説明
・すぐにフォローして安心させる
褒める時:
・大げさなくらいのリアクション
・具体的な行動を褒める
・みんなの前で褒めることも効果的
低学年生の場合、褒めるも叱るもリアクションが大きい方が効果が高いと思います。
②高学年(4〜6年生)への伝え方
高学年では、理由や背景も含めて伝えるようにしています。
叱る時:
・なぜその行動が良くないのか論理的に説明
・将来への影響も含めて話す
・本人に考えさせる時間を作る
褒める時:
・プロセスの素晴らしさを具体的に伝える
・その子の成長を認める言葉
・周りへの影響についても話す
褒める場合も叱る場合も、判断基準は変わりませんが、アプローチには低学年と高学年では違いを持たせます。
また、繰り返しますが、選手一人一人はキャラクターやチーム内での立場も違うので、個人に適したアプローチが必要です。

5. 叱った後のフォローが最重要

①必ずフォローする理由
僕の指導で絶対に欠かさないのが、叱った後のフォローです。
叱りっぱなしでは、子どもは「否定された」「嫌われた」と感じてしまいます。
叱ったのは、その子のことを大切に思っているからこそ。
また、一度叱った後にウダウダ繰り返すことはしません。
わかってくれたら、すぐにいつも通りのユーモアを言える関係に戻します。
②具体的なフォロー方法
・叱った直後ではなく、少し時間をおいてから
・その子の良いところを改めて伝える
・なぜ叱ったのか、愛情があるからだと説明
・「君のことを信じている」というメッセージ
叱った後は選手も落ち込んでいることが多いので、選手に期待している、信じていることを伝えます。
「君ならできるでしょ。」
みたいな感じで、自己肯定感が低くならないようにしなければなりません。
6. NGな叱り方・褒め方

①NGな叱り方
・感情的になって怒鳴る
・人格を否定するような言葉
・他の子と比較して叱る
・結果だけを見て叱る
・叱りっぱなしでフォローしない
叱り方が難しく感じる方は、自分が言われる場合とか、大人だったら、ということをイメージしたら良いかなと思います。
この辺は大人も子どもも関係ありません。
重要なのは、常識的な視点と、相手のことを思う、真剣さです。
②NGな褒め方
・何でもかんでも褒める
・嘘っぽい褒め方
・結果だけを褒める
・他の子と比較して褒める
・具体性のない褒め方
この辺は、心に思っていない言葉を発する行動と似ていますね。
子ども騙しは通用しません。
すぐに見抜かれて、影響力を失います。
③「可もなく不可もなく」の問題
最も避けるべきは、何も言わない「可もなく不可もなく」の状態です。
これでは子どもたちに何の刺激も与えられず、成長のきっかけを奪ってしまいます。
適切に叱り、適切に褒めることで、子どもたちに必要な刺激を与えることが重要です。
余談ですが、『選手に任せる』や『主体性を重んじる』といって、『単なる放任』になってしまうケースがあります。
僕の考えでは、指導者があまりあれこれ言わずに子ども達の主体性を引き出せる条件は、その指導者が強い影響力を持っている状態で、敢えてそうしている場合です。
7. 信頼関係構築のための日常の関わり

①普段からの観察
叱ったり褒めたりする前に、まずは子どもたちをよく観察することが大切です。
・どんなことに興味を持っているか
・どんな時に嬉しそうな表情をするか
・どんな時に困った顔をするか
・どんな性格なのか
これらを知ることで、その子に合った叱り方・褒め方ができるようになります。
②一貫した価値観
指導者として一貫した価値観を持つことも重要です。
僕の場合は「プロセス重視」「人間性重視」という価値観を一貫して持っています。
この価値観がブレないことで、子どもたちも安心して指導を受けられます。
③本気で関わる
子どもたちは、大人が本気で自分たちのことを考えてくれているかどうかを敏感に感じ取ります。
形だけの指導ではなく、本当にその子の成長を願って関わることが、信頼関係の基礎になります。
※コーチングについてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめておきます。
・叱る・褒めるには、まず指導者の影響力と信頼関係が必要
・結果ではなくプロセスを基準に叱り、褒める
・人間性や規律面では妥協せずにしっかりと叱る
・叱った後は必ずフォローする
・年代に応じたアプローチが重要
・「可もなく不可もなく」では子どもに刺激を与えられない
この記事では、子どもの心に響く叱り方と褒め方について解説しました。
一貫した価値観を持ち、プロセスを重視し、信頼関係を大切にすることで、子どもたちの成長を促す指導ができるようになりますので、皆さんの指導現場でも参考にしてみてください!