こんにちは、講師のカズです。
ジュニア年代のサッカー指導では、「子どもたちの主体性を育てたい」と考えている指導者の方が多いと思います。
しかし、実際にはこんな悩みを感じることもあるのではないでしょうか?
・練習中、子どもが自分で判断できず指示を待ってしまう
・「もっと自分で考えて」と言っても、なかなか動けない
・自主性を促したいけど、どこまで任せていいのかわからない
僕自身も、過去には「どうやったら子どもたちが自分で動けるようになるのか?」と悩んだことが何度もあります。
この記事では、「主体性を育てるための基本的な考え方」と「日常指導での実践例」について詳しく解説していきます。
この記事を読めば、子どもたちの行動が少しずつ変わり、より自立したプレーヤーに育てるヒントが見つかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください!
1. サッカーが自然と“人間力”を問う競技である理由

① サッカーというスポーツが内包する「問い」
サッカーは、プレー中に一瞬で判断を迫られるスポーツです。
誰かの指示を待ってから動いていたのでは、間に合いません。
つまり、そもそもサッカーは「自分で考えて動くこと」が求められる競技です。
そして、試合で上のレベルを目指せば目指すほど、技術や戦術以上に「その選手がどういう人間か」が問われる場面が増えてきます。
昔、他のブログでも書いたことがありますが、サッカーはプレーを通して“人間性”を問うてくるスポーツだと感じています。
サッカー以外のスポーツでもそうですね。
だからこそ、技術的な育成と並行して「人としての力=人間力」も育てていく必要があると考えています。
② 主体性は“本能”として持っている
実は子どもたは、生まれながらに「成長したい」「自分でやりたい」という本能を持っていると僕は考えています。
幼い頃に自分で靴紐を結ぼうとする姿や、自分で服を選びたがる姿、きっと誰もが見たことがあると思います。
つまり、「主体性」はもともと子どもが持っている力。
それを大人の関わり方次第で引き出せるか、潰してしまうかが決まってくると思います。
2. 主体性を育てるジュニア指導のポイント

① 子どもを“子ども扱い”しない
僕は、子どもたちをなるべく大人として信頼して接するように意識しています。
「自分でできるでしょ?」「自分で考えてごらん」と問いかけることで、彼らの中にある“考える力”や“責任感”を引き出します。
もちろん、完全に任せるのではなく「必要なときだけサポートする」スタンスも大切です。
② トレーニングで実際に任せる
例えば、以下のような場面で“任せる指導”を取り入れています。
・ウォーミングアップを選手同士で組み立てる
・練習の最後に「自主練時間」を設ける
・試合前にフォーメーションやメンバーを選ばせてみる
これらを行うと、最初は戸惑ったり、うまくいかないことも当然あります。
でもしばらくすると、何とか自分たちで取り組み「形」になってきます。
大事なのは「コーチに言われたから、ではなく自分で考えた」というプロセスだと思います。
③ トラブルも“主体性・自立のチャンス”に変える
例えば以前、こんなことがありました。
県外の遠征先で、ある選手がホテルのオートロックの鍵を失くしました。
そのとき、僕は「自分で探して、それでもなければ自分でフロントに謝ってこよう」と伝えました。
もちろん、最終的には僕がサポートしましたが、最初の一歩を子ども自身に踏み出させることに意味があるかと思います。 つまり自分でできる範囲、もしくはもう少し上のことをやらせる。それでも難しければ大人が介入するタイミングです。
3. 実際の現場での僕の取り組み

① 小学生のある場面から
ある日、小学生の選手が「○○くんが僕のボールを勝手に蹴った」と言いに来ました。
僕はこう返しました。
「自分でその子と話しておいで。どうしてもダメなら、また相談して。」
すると、選手同士で話し合い、解決して戻ってきました。
まずは自分たちで考えて行動させる。
こうした小さな積み重ねが「自分で考えて動く力」を育てていくと思います。
② チームの運営を任せてみる
シーズンの中には、選手たちにフォーメーションやポジションを考えさせる活動もしています。
「なぜこのフォーメーションを選んだのか?」
「もっと良くするにはどうするか?」
こうした問いかけを通じて、選手自身がチームづくりを意識するきっかけになります。
大事なのは「自分で選んで行動して、その結果に自分で責任を持つ」。年齢によってできる範囲は違いますが、日々の練習や試合でも、その機会がないかを探して、できるだけ主体的に動く場面を増やしています。
※自立や主体性を持たせるには、コーチが根気強く「待つ姿勢」が求められます。
が、そもそもの子どもたちに対する影響力を持っていないと、多分上手くいきません。
その辺は「コーチングのスキル」と関わってきます。
ジュニア年代の指導において重要な『コーチング』。
本質的かつ詳しく解説しているので、興味がある方は下記の参考にどうぞ。
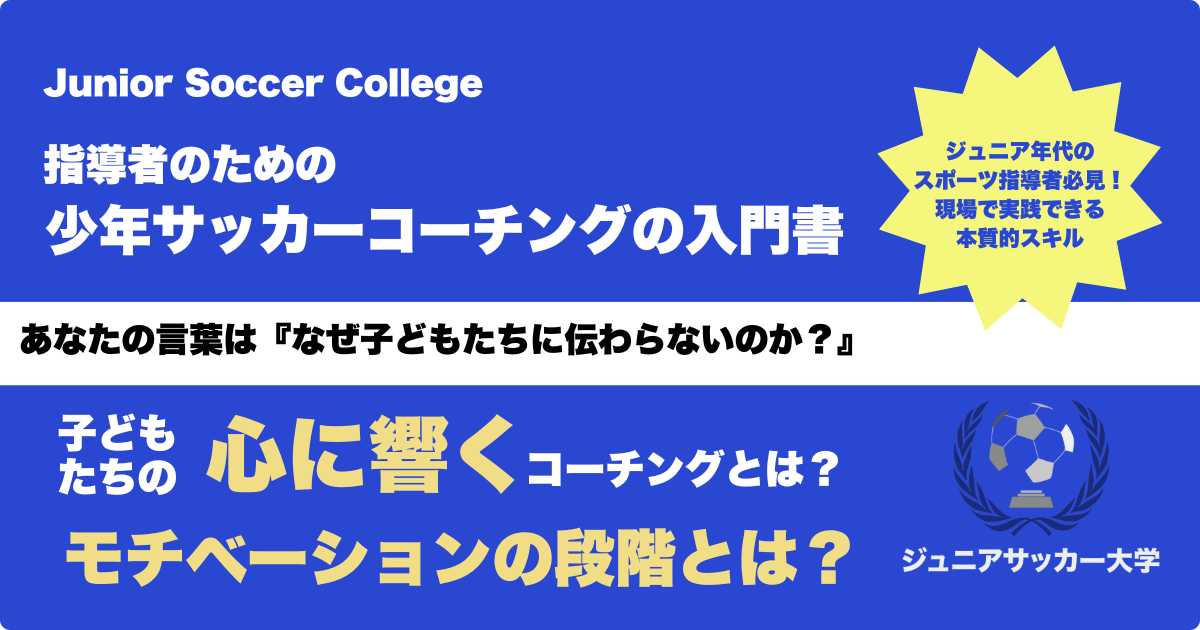
まとめ
・サッカーは“自分で考えること”が求められる競技
・自立・主体性は本来、子どもが持っている力
・任せる・信じる・問いかけることが、主体性を育てるカギ
・小さな場面の積み重ねが、自立した選手を育てる
この記事では、「少年サッカーにおける自立・主体性の育て方」について解説しました。
僕たち指導者は、サッカーの技術を教えるだけでなく、“自分の人生を自分で切り開いていける力”を育てる存在でもあります。
日々の小さな関わりの中にこそ、子どもたちの成長のチャンスがあります。
ぜひ、皆さんの現場でも「自分で考える」「自分で行動する」ための問いかけや任せる指導を、少しずつ取り入れてみてください!








