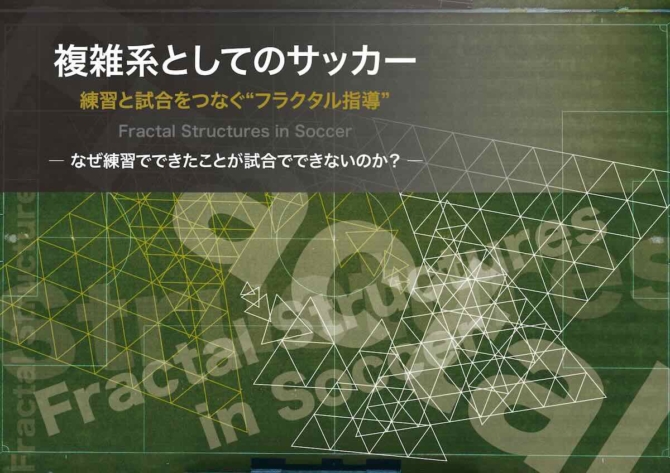複雑系– category –
-

複雑系としてのサッカー:練習と試合をつなぐ“フラクタル指導” ④
「パスコースがない時はドリブルで時間を作る」このような原則が、ロンドでも試合でも変わらず機能することに気づけば、プレーは一気にシンプルになります。 この章では、どの場面でも“変わらない判断軸”を持たせるための「原則としてのフラクタル性」について解説しています。 -

複雑系としてのサッカー:練習と試合をつなぐ“フラクタル指導” ③
サポートの三角形、守備時のスライド――。 サッカーでは、局所的なプレーの構造が、試合全体と相似的に繰り返されます。 これは「構造としてのフラクタル性」であり、選手の理解やプレーの安定感を支える重要な土台となります。 形や動きにおける“構造の相似性”を意識することが、指導の質を一段高める鍵になります。 -

複雑系としてのサッカー:練習と試合をつなぐ“フラクタル指導” ②
サッカーの本質とは、1つでも欠ければ成立しない要素です。 人数が変わってもこの本質が保たれていれば、8人制も5人制も“フラクタルな関係”としてサッカーは成立します。 本章では、この考え方が指導の土台になる理由を解説します。 -

複雑系としてのサッカー:練習と試合をつなぐ“フラクタル指導” ①
フラクタルとは「スケールが変わっても繰り返される相似構造」のこと。 自然界にも存在するこの現象は、実はサッカーにも当てはまります。 本章では、複雑系という前提のもと、サッカーにおける“フラクタルな構造”の意味と可能性を解説します。 -

【執筆中の電子書籍について】複雑系としてのサッカーを考える
こんにちは、講師のカズです。今回は僕が現在執筆中の電子書籍についてお話ししたいと思います。 今回の書籍は、サッカーを「複雑系」として捉えたときに、どのような指導方法が考えられるのかをテーマにしています。僕自身、10年以上前から「サッカーは複... -

自己組織化と創発とは?【複雑系としてのサッカー】分かりやすく解説
サッカーを“複雑系”として捉えることで、自己組織化や創発現象という観点から選手やチームの動きを深く理解できます。本記事ではその基礎を分かりやすく解説します。 -

サッカー指導の基礎理論【複雑系としてサッカー】基本的な考えを解説
サッカーは「複雑系のスポーツ」。 選手の動きとチームの機能は、単純な足し算では説明できません。 本記事ではその理由を理論と事例で解説します。
12