こんにちは、講師のカズです。
この記事は、X(旧Twitter)でいただいたご質問をもとに、「状況認知とプレー判断」「指導方法」について解説します。
以下、ご質問の要約です。
・ボールが自分に来る前に状況を見ているが、その時点から味方や相手の位置が変化している。
・しかし、その最初に見た状況をもとにプレーを決めてしまっているため、ズレたり、奪われたりすることがある。
・ボールを受ける直前や受けた直後に、もう一度状況を見てプレー判断を更新できるようにしたいということ。
・そのために必要な「意識の持ち方」や「見る癖をつける練習方法」を知りたい。
・また、「(自分にボールが来る瞬間)は相手マーカーしか見れない」という認識が正しいかどうかも確認したい。
ジュニア年代の指導では、「ボールを受ける前にまわりを見なさい」とよく言いますよね。
でも、実際に子どもたちは「見たのにうまくいかない」「見た状況と違って失敗した」ということが起こります。
僕自身も、指導現場でこうした悩みに直面してきましたし、どう伝えたらいいのか迷うこともありました。
今回のご質問では、以下の点について解説します。
・ボールを受ける前に状況を見たのに、プレーがうまくいかないのはなぜ?
・状況が変化していた場合、どう判断を修正すればいい?
・認知や判断の「癖」はどうやってつけるの?
・ボールが来る瞬間には、相手マーカーしか見えないのでは?
この記事では、こうした疑問に対して、僕の考えと指導現場での工夫を交えてお答えします。
プレーの質を高めたい指導者の方にとってヒントになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください!
1. 状況が変わる中で、判断をどう更新するか?

まず、ご質問の本質は「状況は常に変化するのに、プレー判断が更新されていない」ことです。
ボールが来る前に見た情報に基づいてプレーを決めてしまい、ズレやミスが起きる、という問題ですね。
このような現象は、オン・ザ・ボール(ボール保持)の局面において「判断の柔軟性」が欠けている状態です。
つまり、プレーを実行するタイミングでの「無意識の選択肢」が少ない状態。
ポイントは以下の通り。
・ボールが来る前に周囲を見ておくことは良い。
・しかし、ボールが来た時に状況が変わっていたら、判断も更新する必要がある。
・それができないのは、「無意識レベルの判断ストック」が少ないから。
ジュニア年代では、判断力を高めるというより「無意識にやれる選択肢を増やす」ことが大切だと思っています。
そのためには、繰り返しの経験と、選択肢を少しずつ増やす指導が必要です。

2. 「何が見えているか・いないか」を観察する
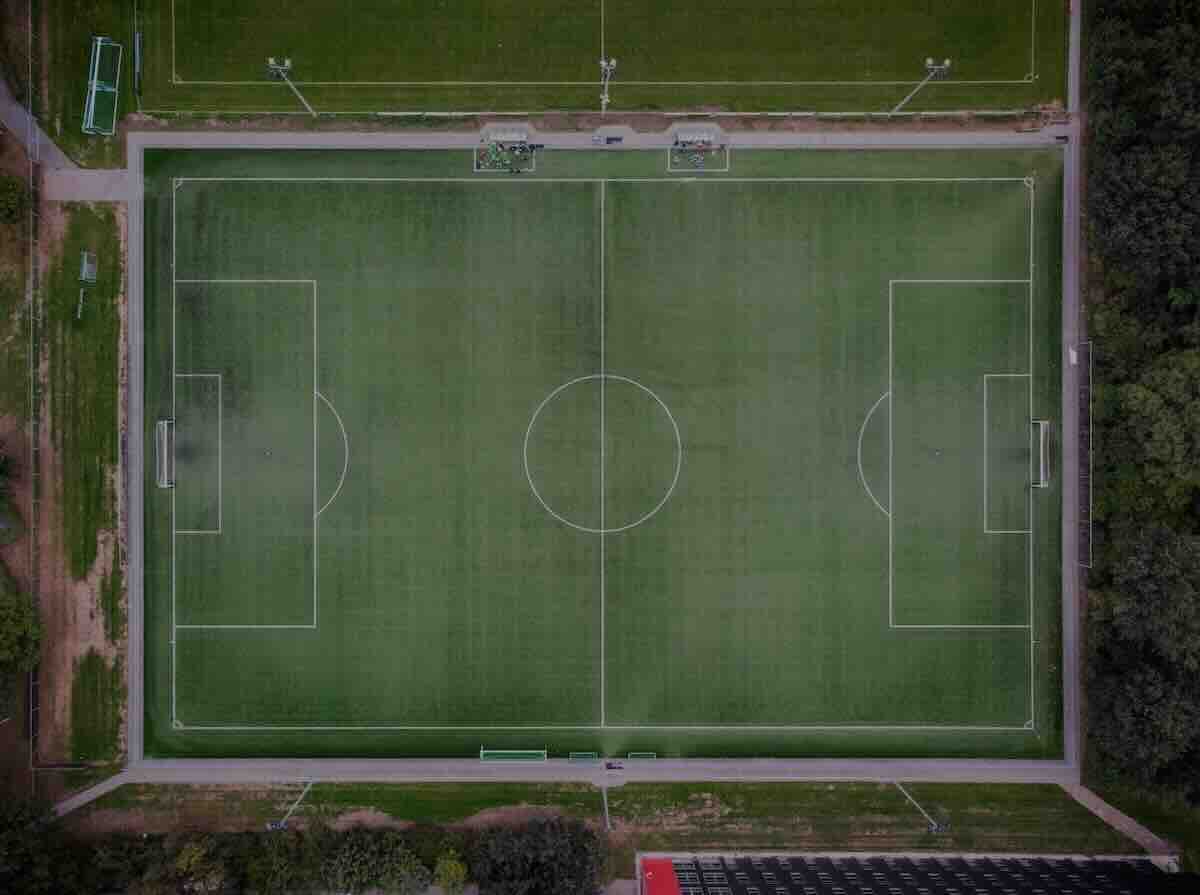
僕の指導では、選手のプレーを見ながら「この子の頭の中で何が起きているか?」を常に想像しています。
以下の2つを観察します。
・何が見えていて、何が見えていないのか?
・どの判断は無意識でできていて、どれは意識しないとできないのか?
たとえば、センターバックの選手が、サイドバックがフリーにも関わらず、中盤へ縦パスをつけて奪われた。
その場合、「まずサイドバック見てごらん」と伝えます。
逆に、ボランチとサイドは見えているけどフォワードの動きが見えていない選手には、
「まずFWを優先的に見よう」と伝えます。
このように、プレーの“詰まりポイント”を見つけて、そこに“意識”を当てる。
このようにして「判断のストック」を増やすようにしています。

3. 認知を高めるトレーニングはあるのか?

「見る癖をつける練習はありますか?」という質問もいただきました。
正直に言うと、僕は「認知を高めるための特別な練習」はしていません。
その理由は、サッカーは“複合的なスポーツ”だからです。
見る・考える・動く、すべてが同時進行です。
だからこそ、僕は「グローバルトレーニング(複合型の実戦的な練習)」をよく行います。
『認知』という部分だけを切り出してトレーニングするのではなく、グローバルトレーニングの中で「認知の部分」に問題があるならそこにフォーカスするイメージです。

4. ボールが来る瞬間には何が見えるか?

もう一つの質問「ボールが来る瞬間には相手マーカーしか見えないのでは?」についてですが、
これは 選手のレベルによりけりです。
・相手マーカーすら見えていない選手もいる
・相手と自分の位置関係を見てプレーできる選手もいる
・さらに一歩先、次のパスコースまで見えている選手もいる
つまり、「何をどこまで見れるか」は、その選手の“現在のレベル”によります。
だからこそ、選手が“どこまで無意識で判断できるか”を見極めて、そこに少しだけ新しい意識を乗せていく。
このようなアプローチをしています。
5. 無意識を育てるための指導アプローチ

ここまでの話を整理します。
・ボールを受ける前にイメージを持つのは大事
・でも状況が変わったら、それに応じて判断を修正する必要がある
・修正できないのは、「判断ストック(=無意識レベル)」が足りないから
・それを増やすには、“考える要素を減らした状態”から徐々に育てていく
僕の場合、最初は「選択肢を絞って」トレーニングし、無意識レベルでできることが増えてきたらそこに少しずつ足していくイメージです。
それがやがて“考えなくてもできる判断できる”ようになっていきます。
6.まとめ
・状況は常に変化する。見た情報に固執せず、判断を更新する力が必要
・指導者は、選手が「何が見えていて、何が見えていないか」を観察することが大事
・特別な“認知トレーニング”よりも、複合的な実戦型トレーニング(グローバル)がおすすめ
・判断を早くするには「無意識レベルの選択肢のストック」を育てる必要がある
・プレーミスが出たときは、「どこで迷ったか?」を観察して、意識ポイントを1つ伝えること
ジュニア年代の選手にとって、「判断を変える」「選択肢を増やす」というのはなかなか難しい部分です。
また、テクニックレベルとも関係していきます。
だからこそ、僕ら指導者が少しずつ“意識”と“無意識”を整理しながら、段階的に育てていくことが大切かなと思います。
この記事が、選手の判断力を高めたい指導者の方のヒントになればうれしいです!








