こんにちは、講師のカズです。
ジュニア年代のサッカー指導では、選手の主体性や自主性を育てることがとても重要です。
しかし、従来の線形的な指導法では、なかなか子どもたちの本当の成長を引き出すことができません。
僕自身、過去には積み上げ式のトレーニングで選手を伸ばそうと試行錯誤していた時期がありました。
しかし、エコロジカル・アプローチと複雑系の考え方を取り入れてから、選手たちの急激な成長を目の当たりにして、これまでの指導観が完全に変わりました。
しかし、以下のような悩みを持つ指導者の方も多いのではないでしょうか。
・練習でテーマを決めても選手が思うように成長しない
・選手の主体性や自主性がなかなか育たない
・トレーニングの効果が試合で発揮されない
この記事では、複雑系としてのサッカー指導の基本的な考え方から、エコロジカルアプローチの具体的な効果まで詳しく解説します。
この記事を読めば、従来の線形的指導から脱却し、選手の非線形的な成長を促す指導がスムーズになり、子どもたちの可能性が格段に広がると思いますので、最後までご覧ください。
1. エコロジカルアプローチの爆発力を実感した現場体験

①教えなくても動きが出る驚きの現象
最近の週末の試合で、まさにエコロジカル・アプローチの効果を痛感する出来事がありました。
ジュニアサッカーLabに参加している指導者の方から「エコロジカルな制約を実施したところ、全然教えていないのに素晴らしいプレーが出てすごく鳥肌が立ちました!」というコメントをいただいたんです。
これはまさに複雑系の特徴である「創発現象」なんですね。
指導者が意図していないような素晴らしいプレイが突然現れる。
このような現象を僕も自分のクラブで何度も経験しています。
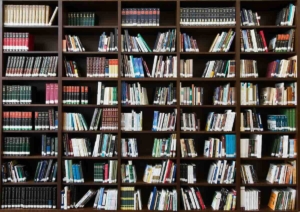
②選手が急に伸びる瞬間の正体
僕のクラブでも、選手が急にうまくなったり、組織が急に高連携プレイを繰り出したりする現象を頻繁に目にするようになりました。
重要なのは、そういった練習に重点を置いていないということです。
従来の線形的な指導では「これを教えたからこうなった」という因果関係を求めがちですが、複雑系では原因と結果がそう単純ではありません。
1+1=2ではない成長が起こるります。
③非線形的成長の仕組み
エコロジカルアプローチでは、制約を設けることで選手たちが探索期間に入ります。
この時期は一見ぐだぐだしたプレイに見えますが、実は選手たちが最適なプレイを探している重要な時間です。
その探索期間を経て、突然自己組織化が起こり、創発現象が生まれます。
これが選手たちに躍動感をもたらし、指導者が思ってもいなかったプレイを生み出すメカニズムです。
2. 複雑系思考vs線形思考の根本的違い

①従来の積み上げ式指導の限界
従来の指導でよくあるのが、テーマを決めて、そのエラーが出るようなオーガナイズを工夫し、選手に質問を投げかける方法です。これは完全に線形的な思考に基づいています。
例えば、クローズドスキル(敵がいない状態)からオープンスキル(敵がいる状態)へと段階的に進めるトレーニング構成も、選手の成長が線形であるという前提に立っています。
②複雑系の基本特性を理解する
複雑系には重要な特性があります。
それは「ブラックボックス性」です。
完全な予測が不可能で、完全にコントロールすることもできません。
しかし、これは欠点ではなく、複雑系の本質的な特性。
サッカーのプレイ、チームプレイ、チームマネジメント、クラブ運営まで、すべてが複雑系です。
この特性を理解せずに中央制御型で指導すると、システムが望ましい挙動を示さなくなります。
③1+1=2ではない成長を受け入れる
線形思考では「これをやったらこうなる」という明確な因果関係を求めます。
しかし複雑系では、1の練習をしても2になることもあれば、突然4や5になることもあります。
逆に停滞期もあります。
これを理解していないと、停滞期に不安になって余計な介入をしてしまい、せっかくの成長の芽を摘んでしまう可能性があります。
④中央制御型から分散型への転換
複雑なシステムに対して中央制御を強くすると、システムが機能しなくなります。
これはサッカー指導においても同じです。
指導者がすべてをコントロールしようとするのではなく、適切な制約を設けて選手の自己組織化を促すことが重要です。
3. 日本独自の育成システムの可能性

①6-3-3システムの隠れたメリット
日本の教育システムである6-3-3制は、実は複雑系の考え方やエコロジカル・アプローチにとって非常に有利な環境を提供しています。
特に中学3年間の余裕は、他国では得られない大きなアドバンテージです。
スペインなどでは1年ごとに昇格・降格があり、毎年シビアな結果が求められます。
しかし日本では、中学1年生から絶対に勝たなければならないというプレッシャーは比較的少ないですよね。
②余裕ある指導が生む真の成長
この余裕こそが、複雑系アプローチの真価を発揮させる環境なんです。
目の前の成果を求めるあまり大事な育成要素を失うリスクを避けることができます。
僕も現在U-13を指導していますが、この余裕を持った指導ができることで、選手たちの本質的な成長に集中できています。
これはヨーロッパの仕組みでは真似できない日本独自の強みだと思います。
③ヨーロッパ偏重からの脱却
サッカー界では「ヨーロッパが正しい」という風潮がありますが、すべてを鵜呑みにする必要はありません。
学ぶべきものは学びつつも、日本の良さを再評価し、独自のアプローチを構築することが重要です。
複雑系の考え方は、この日本の環境において世界トップを目指すために、非常に適していると確信しています。
④新しい時代のスタンダード
複雑系思考、エコロジカルアプローチは間違いなく今後の時代のスタンダードになるでしょう。
30年の指導経験を通してやっと辿り着いたこの考え方を、多くの指導者の方に知っていただきたいと思います。
日本の育成において起きている問題の多くは、複雑系を理解していないことに起因しています。
逆に言えば、複難系を理解すれば、もっともっと良くなる可能性が無限大に広がるということです。
まとめ
この記事では複雑系としてのサッカー指導について解説しました。
重要なポイントをまとめると以下の通りです。
・エコロジカルアプローチは選手の非線形的成長を促す
・複雑系の特性を理解した指導が新時代のスタンダード
・日本の6-3-3システムは複難系アプローチに最適な環境
・線形思考から複雑系思考への転換が指導革命の鍵
従来の積み上げ式指導から脱却し、複雑系として選手と向き合うことで、これまでにない成長を引き出すことができます。
皆さんの指導現場でも、この新しい視点を試してみてください!
※こういった議論を活発に行なっている『ジュニアサッカー大学Lab』









