こんにちは、講師のカズです。
ジュニア年代のサッカー指導で、時々ある議題。
『リフティング練習をさせるべきかどうか。』
◾️コーチ
・サッカーはサッカーをしないと上手くならないよ。
・リフティングは状況判断がないからサッカーではない。
・ボールを扱うテクニックは重要。その基礎がリフティングだ。
◾️保護者
リフティングできないと試合に出してもらえない。
どうやったら上手くなるのかな。
何回くらいできたらいいのかな。
そもそもリフティングの練習は必要なのでしょうか?
僕自身は25年の指導経験の中で何周もこの問題について考えました。
バルセロナにコーチ留学中に、スペイン人はリフティングが下手でもサッカーが上手いなと感じた経験と日本人の特性という観点からも考察。
僕の場合はジュニア年代の指導においては練習中に短い時間でリフティング練習を取り入れるのですが、その狙いは別のところになります。
先に結論をいうと
✔︎リフティング練習がサッカー上達に欠かせない内発的動機づけを強化するツールになる
この記事を読んで頂ければ、リフティング練習の効果的な方法だけでなく、子どもたちがサッカーが上手くなるために必ず必要な内発的動機づけの強化の仕方がわかります。
動画で解説
1. なぜリフティングを練習するのか
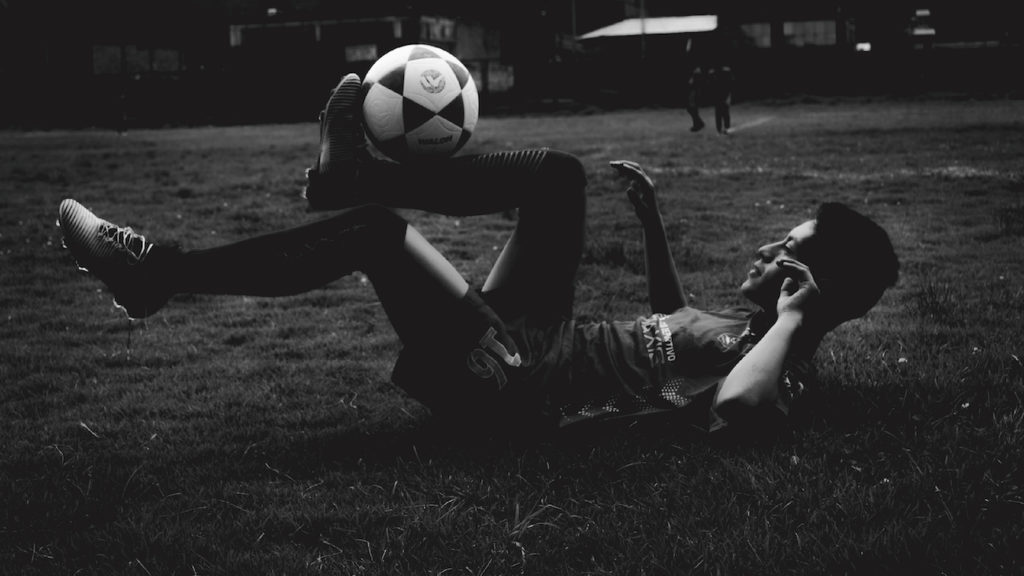
リフティングに関しては指導者によって意見が分かれます。
基本的なことだからしっかりと練習した方が良い。
サッカーはサッカーをすることで上手くなるからリフティングを練習しても意味がない。
これらはどちらが正解でしょうか。
① リフティングの効果
一般的に言われるリフティング練習から期待できる効果は以下の通りです。
・ボールフィーリング(感覚)を高める
・コーディネーション(運動神経)の向上
・浮いたボールの扱いが上手くなる
一般的かどうかはさておき、集中力を高めるなんてこともありますね。
リフティングが上手い=サッカーが上手いではない
現在の定説では
リフティングが上手い=サッカーが上手い
わけではありません。
僕も同意です。
サッカーの基礎テクニックであるとも考えていません。
基本的なテクニックは他にもたくさんあります。
② サッカーのパフォーマンスとの因果関係が証明できない
リフティング自体、継続して練習すればある程度は誰でもできるようにはなります。
いろんな部位を使ってできるようになる、回数が増えることで上達を数値化できます。
しかし、実際の試合でのパフォーマンスとの因果関係を証明することはできません。
リフティング練習をしたことでボール感覚が良くなったのか、それとも別の練習によってそうなったのか。
なので「多分こういう効果があるだろう」という仮説でしかない。
なぜ因果関係を証明できないのに練習するのか
もちろん因果関係がある、という前提で指導するコーチもいます。
僕自身「できないよりできた方が良い」と思いますが、長時間チームの練習として取り組むことはしません。
他にもやるべきことが山積みで、多くの時間を割く余裕がないからです。
③ リフティングをツールとして使う
しかし僕は、先ほどの期待できる効果以外にもいくつかのメリットがあると考えてます。
しかもそれは「サッカー上達のための根本的な方法」です。
それは「内発的動機づけ」を強化するツールになるということ。
僕のケースで言うと、リフティング練習における効果を期待しながらも、子どもたちのサッカーに対するモチベーションを上げること。
意識を高めるためのツールとして使っているのが重要なポイントです。
2. リフティングを使って内発的動機づけを促す方法
内発的動機づけがあまり理解できていない方は、下記の記事を先に読んでください。

なぜリフティング練習を行うことで内発的動機づけができるのか。
厳密に言えば内発的動機づけ後の「選手自身が自発的に努力する」最初のツールとして使っています。
では、僕が実際に行なっている指導方法を紹介します。
① サッカーに対するモチベーションを引き上げる
僕が担当するチームでは、選手のサッカーに対するモチベーションが「もっと上手くなりたい」という段階の選手が多いです。
そこから次のステップを踏ませるために、
・どうやったらもっと上手くなるのか
・上手くなるためには何をしないといけないか
・良いサッカー選手のパーソナリティはどのようなものか
こういったことを、練習でのミーティング、試合前後、雑談を通じて選手が気づいていくように促したり諭します。
※モチベーションがどの段階かをきちんと見極めましょう。

選手に自信を持たせ、足りないものを明確にし、もっと上手くなりたいという欲求を引き出す。
そしてそのためには日々の努力が必要であることを理解させます。
②【重要】リフティング練習を通じて努力による成功のプロセス実感させる
努力することが必要だというメンタリティを持たせながら、練習の最初にリフティングを入れます。
自ら簡単なお手本も示し、
「最初は誰もできないこと」
「やれば誰でもできること」
「やろうとするプロセスが重要であること」
を諭します。
短い時間で選手に促し、あとは自分でやりなさいと、決断の意思を選手に渡します。
宿題ね、と伝えることはありますが、それができるようになるかどうかは見ていません。
それによって選手のモチベーションが高まっているかどうかを見ます。
内発的動機づけができていれば、ほとんどの選手は地道に取り組みます。
そして最初に言った通り「リフティングは誰でもある程度はできるようになります」。
そうすると、子どもたちは自らの努力によって「できなかったことができるようになる」という達成感を味わいます。
この良いスパイラルを循環させることが目的です。
自分の努力によって自分が成長できるという充実感
これによって努力することの重要性、自分にもできるという肯定感。
そこからさらに上手くなりたい、そのために努力できるメンタリティを育みます。
3. ジュニア年代での上達にはチーム練習以外の自主練習も必要
以下の記事を読んで頂ければ、チーム練習を週に何回やるべきか、個人的な自主練習とは何かがわかります。

① リフティング練習でなくても良い理由

僕がリフティング練習を取り入れるのは「努力によって成功のプロセスを実感させる」と解説しました。
つまり、達成感を得るにはリフティングでなく、別のものでも構いません。
フェイントやターン、浮いたボールのコントロールなど。
これらの閉じたスキルというものは練習すれば誰でもできます。
また、指導者にとっては限られた練習時間の中で、個人的なスキルのトレーニングに時間を割きたくないという方にはこの方法は有効です。
内発的動機づけは高められるし、選手が自分で基礎テクニックをマスターしてくれる。
チームの練習時間をチームのトレーニングに当てることができますね。
② リフティングの目標回数達成で試合出場はダメ
僕の考えではリフティングとゲームでのパフォーマンスの因果関係が証明できないということ。
ぼくがリフティング練習をするのは内発的動機づけを強化するためだと書きました。
練習中に
「いついつまでに〇〇回できるようにしよう!」
と言うことはありますが、それを達成していないからといって試合に出さないということはしません。
なぜならゲームでのパフォーマンスと因果関係が証明できないし
やろうとする努力=プロセスに価値があるから。
なので選手を評価するときにもリフティングが上手いということを加味しません。
ただ、サッカーに対するモチベーションは選手選考の時などに判断材料にいれます。
あくまでもゲームでのパフォーマンスが重要です。
③ リフティングの回数はベースができるを目標に
ここまで読んで頂いた方の中には、
具体的に何回くらいできたらいいのかな
と思う方もいると思います。
僕はこだわりがないので少し視点がずれているかもしれませんが、各部位でベースができればOKだと思います。
インステップ(交互)20回
インサイド(交互)20回
アウトサイド(片足)10回
もも(交互)20回
ヘディング 10回
この数字は経験値的な数値です。
基本的にこれくらいできればベースはできています。
あとは集中力があれば何回でも続くはずです。
基本的に毎回コンスタントにこの数字が出せれば、プラスで2,30回できると思います。
あといろんなところを使いながら50回くらいでもいいでしょう。
それといろんな技に挑戦するのも楽しいし、できた時の達成感があるので、自主的に取り組むには良いと思います。
遊びながらできますし。
気合い入れて1000回でも良いかもしれません。
どうしても「リフティングを重要視してもっとできるようになった方が良い」と考えている場合は、リフティングにこだわりのある方に話を聞きましょう。
僕のリフティングに関するスタンスは最初の方に書いたとおりです。
(※今後変わるかもしれません!)
4. まとめ
今回はリフティングというものを、あまり語られない視点から解説しました。
やはり子どもがサッカーが上手くなるためにもっとも重要なことはモチベーションだと思います。
つまり内発的動機づけ。
これがないと上手くなりません。
サッカーコーチの役割はサッカーを教え、トレーニングをオーガナイズするだけでなく、モチベーターとしての役割も重要だということを理解してもらえればと思います。
ぜひ実践してみてください!








